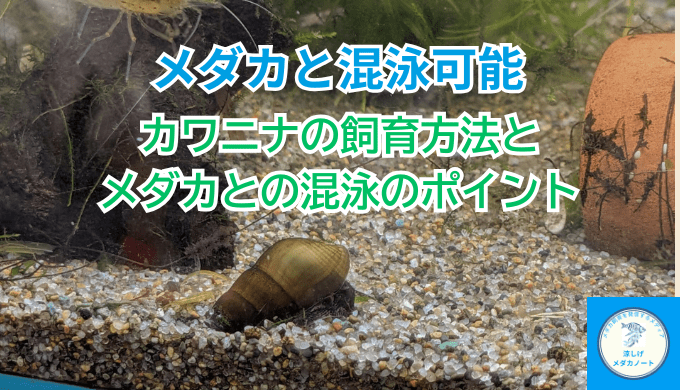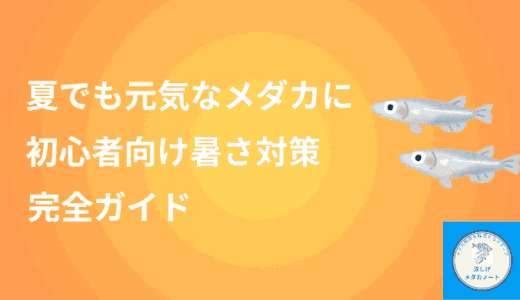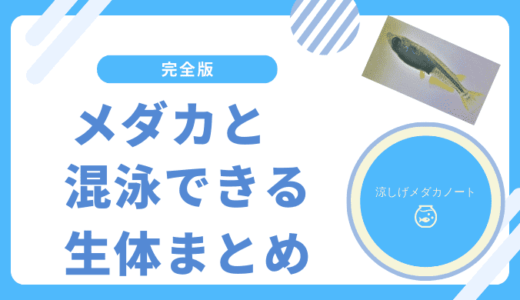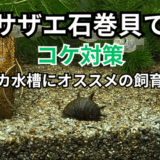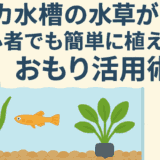著者:りょうた
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ホタルの幼虫のエサとして知られるカワニナの飼育。淡水に生息する巻貝で、コケや残餌を食べるため、水槽の清潔さを自然に維持してくれます。
見た目も落ち着いた印象で、元々日本にも生息していることからメダカ飼育やビオトープとの相性が抜群。今回はそんなカワニナをメダカ水槽で混泳させたときの飼育状況などを解説しました。
カワニナの特徴・飼育環境
カワニナの基本的な特徴
| 体長 | 約2〜4cm |
| 生息地 | 日本各地の清流・湧水地 |
| エサ | コケ、残餌、有機物 |
| 水温 | 15℃~25℃が理想(高温に弱い) |
| pH | 中性~弱アルカリ性 |
| 混泳可能な生体 | メダカ、ミナミヌマエビ、タニシ等 |

カワニナは日本各地の清流や湧水地に生息する淡水の巻貝で、体長は2〜4cmほど。落ち着いた黒褐色の殻を持ち、静かに底砂を這う姿が特徴です。カワニナの飼育に適した環境は、水温15〜25℃、中性〜弱アルカリ性の清潔な水。酸素が豊富で、緩やかな水流があると健康に育ちます。メダカやヌマエビなどの小型生体と共存しやすく、コケや有機物を食べることで水質を維持します。屋外ビオトープでも人気が高く、自然な景観づくりに欠かせない存在です。
カワニナのオスメスの見分け方

カワニナは外見においてオスとメスで明確な違いがなく、見ただけで区別することは困難です。そのため繁殖を期待する場合は、ある程度まとまった数での飼育がオススメです。

たとえばタニシであれば触覚がまっすぐならメス、片方が曲がっていればオスという区別ができますが。
環境が合えばいつのまにか稚貝がいる
カワニナは先述の通り卵ではなく稚貝を産むので、気が付いたら水槽内に違いがいることもあります。最初は1㎜くらいと肉眼でかろうじて見える大きさですが、1か月もたつと4,5㎜にもなり普通に見えたり見た目も大人のカワニナと似た感じになります。

水槽の壁をつたっていることが多いですが、水草などの裏や間に紛れていることもあり気が付けば10匹以上稚貝がいることもあります。
屋外ビオトープでも飼育可能

カワニナは室内だけでなく、屋外のビオトープでも飼育可能です。屋外の方がエサになるコケ・藻が発生しやすかったり、野生の環境に近いので、相性が良い部分もあります。
ただし秋から冬にかけては水温が下がる影響で活動が鈍くなったり、底砂の中にもぐってしまうこともあります。
カワニナのメリット
コケや汚れを食べてくれる
カワニナの飼育で最も大きなメリットは、水槽やビオトープ内のコケ・残餌を食べてくれることです。ガラス面や底砂に付着した藻類をゆっくりと食べるため、見た目が清潔に保たれます。人工的な掃除道具を使わなくても、自然な形で水槽を維持できるのが魅力。メダカの餌の食べ残しも処理してくれるため、悪臭や水質悪化を防ぐ効果もあります。
メダカとの相性が良く、自然な生態系が作れる
カワニナは性格が温和で、他の生体を攻撃することがないため、メダカやミナミヌマエビとの混泳に最適です。メダカが泳ぐ中層域、カワニナが活動する底層域とで住み分けが自然にできるため、生態系バランスが崩れにくいのが特徴。さらに、カワニナが有機物を分解する(食べる)ことでバクテリアの働きが安定し、水質が良好に保たれます。結果として、メダカが元気に過ごせる環境づくりに大きく貢献します。
カワニナのデメリット・注意点
繁殖して、数が増えすぎる場合もある
メダカ飼育に用いられる買いには他にもコケ取り効果が高いことで知られる石巻貝がいます。石巻貝は卵を産むこともありますが、淡水では孵化しないため水槽内に卵が残り続けます。気が付けばそこそこの数の卵がついていることもあり、気になるところです。

一方でカワニナは条件が整うと容易に繁殖し、短期間で数が増えすぎることがあります。石巻貝と異なり卵胎生(卵ではなく稚貝を産む)のため、卵をそこら中に産み付けて水槽の景観を悪くすることはありません。
ただし、環境が合えば繁殖力もある程度あるため、稚貝が増殖してにぎやかになるケースも。増えすぎると酸素量が減少したり、水質バランスが崩れる原因になるため、定期的な間引きが必要です。水槽内の景観が悪くなるほど増えることは稀ですが、観察しながら適切な数を保つことが、カワニナの飼育を長く楽しむコツです。

ちなみにうちの水槽では、カワニナを導入してから1か月で8匹の稚貝を確認しました。個人的な体感では、タニシよりは増えますね。
高温に弱い(特に真夏)
カワニナの飼育で注意すべきもう一つの点が、高温への弱さです。水温が30℃を超えると活性が低下し、最悪の場合は死亡することもあります。真夏の直射日光下では水温上昇が早いため、日陰を作る、浅い鉢を避けるなどの工夫が必要です。特に屋外ビオトープでは、ミズトクサやウォーターバコパなど背の高い水草やホテイアオイなどの浮き草を使って遮光すると効果的。夏場の管理をしっかり行えば、カワニナも安定して健康に過ごせます。
水槽から脱走しないように注意
カワニナに限らず貝類全般に言えますが、水槽からの脱走には注意しましょう。油断していると水槽から飛び出していることもあります。

動きが遅いのでよほど長時間放置しなければ完全に飛び出すことはないですが、不安な方は水槽用のフタをしておきましょう。
よくある質問
- カワニナはメダカと一緒に飼える?
- はい。共生可能です。カワニナは温和で、他の生体を攻撃しません。
- カワニナのエサは必要?
- 基本的には自然発生するコケや残餌でOK。コケが少ない場合はプレコフードや湯通ししたほうれん草を少量与えます。
- 冬場はどうする?
- 冬眠状態で越冬可能。ただし凍結の恐れがある地域では屋内に避難させましょう。
まとめ
カワニナは元々生息環境がメダカに近い部分もあるので、メダカと飼育することは問題ありません。高水温に弱い点や意外と繁殖力がある点に気をつければ、水槽内のコケを取るなどのメリットもあります。
メダカ飼育で貝類を入れたい方は、ぜひカワニナも導入してみましょう。

以下の記事でメダカと混泳できる生体をまとめて紹介しています。
メダカ用品のお買い物をおトクに!
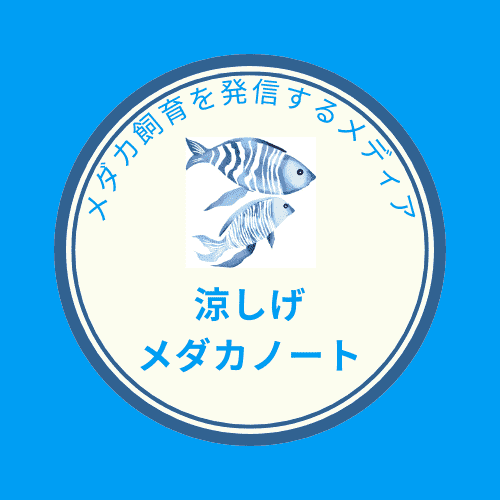 涼しげメダカノート
涼しげメダカノート