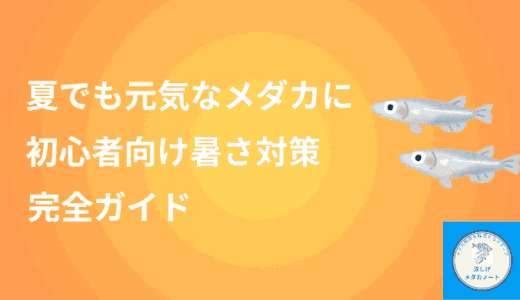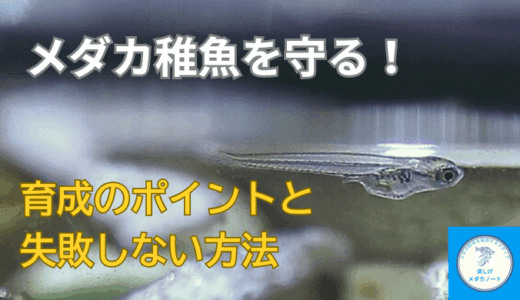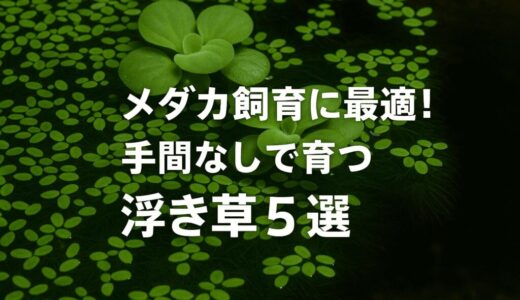著者:りょうた
この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
屋外の水槽(ビオトープ)で緑の糸っぽい、ドロドロした藻がありませんか?
実はこれ『アオミドロ』って言います。屋外の水槽で発生することが多いですが、放置すると水中を覆いつくしメダカへの被害も出る厄介なものです。
今回はアオミドロとはどんなものかや対策を解説しています。
アオミドロとは


アオミドロは藻の一種で水槽内はもちろん富栄養化した川や沼などでも見られます。水槽では強い光や水中の養分(富栄養化した状態)がもとになって発生するため特に屋外の水槽で見られることが多いです。
アオミドロに毒はないですが、育つと水槽中を糸のようなもので覆いつくしてメダカなどが絡まってしまったり景観的にも良くないです。そのため、メダカなど観賞魚の飼育ではアオミドロは除去することが推奨されています。
アオミドロが発生する原因
アオミドロは直射日光を受けて光合成をすることで成長します。特に夏は日差しが強く、日照時間が長いためアオミドロなどの藻が発生しやすい季節でもあります。

夏は要注意ですね。
メダカなどの生き物がいることで出てくるフンであったり、直射日光により水中にはどんどん養分(+植物プランクトン)が増えます。適度にある分には、養分が過剰になった状態がいわゆる『富栄養化』と言われる状態です。
窒素・リンなどの栄養塩類は湖沼や海域の生態系を構成する細菌や動植物にとって必須な元素です。しかし,公共用水域への汚濁負荷物質の流入が高まり,水中の窒素・リンが必要以上に増えると,それを栄養として利用する植物プランクトンが急速に増えてきます。このような状態を富栄養化といいます。富栄養化の影響でアオコなどが異常増殖すると,水中の溶存酸素が不足し,魚類や藻類が死滅して水環境が悪化してしまいます。さらに,水道水などとして利用している場合,浄化がたいへんなだけでなく,異臭味などの問題も起きてきます。
コラム「富栄養化と有毒アオコ」国立環境研究所
河川での富栄養化としては特に『アオコ』が話題に挙がりますが、同じような原理でアオミドロも発生します。水中に適度に養分があれば良いのですが、養分が多すぎること(富栄養化)によって、
- 酸素が不足⇒生体が死滅
- 異臭がする場合もある
などの実害があります。水換えなど、普段からの水質の調整が重要ですね。

かといって大規模に何かをやる必要もないので、まずは普段から水槽や生き物を観察しましょう。
アオミドロがあることのデメリット

アオミドロは細い紐のような見た目で水草や壁などあらゆるところから発生します。発生初期はぱっと見ではあるかどうかわからないレベルですが、そのまま放置しておくと大きく太くなり水槽の中が見えづらくなります。
せっかくのメダカも観察しづらくなるので、放置しすぎず早めにアオミドロは取り除きましょう。
ヒモのような見た目のため、メダカなどが絡まることもまれにあります。実際僕の水槽でもアオミドロを放置してた時期はメダカが絡まっていたことは何度かありました。大人のメダカもそうですが、特に稚魚はアオミドロに絡まって抜け出せなくなりそのまま死ぬ可能性もあります。
そのため、特にメダカの稚魚がいる水槽はアオミドロの発生に注意しましょう。
アオミドロの対策でできること

アオミドロも藻の一種とは言いますが要は植物で日光で光合成をすることによって成長します。逆に言えば日光を遮断(当たる量を減らす)することによってアオミドロの成長を抑制することもできます。屋外で有効なのは、
- 水槽を日の当足らない場所に(一時的に)移す
- すだれなどで日陰を作る
などが有効です。ただし日光を完全に遮断すると他の水草やメダカにも悪影響が出るので、あくまで日光に当たる時間を『減らす』というのがポイントです。

実際にすだれを導入するとアオミドロが減ったように感じます。

アオミドロはある程度成長するとそれなりに固くなるので手で取り除くのが基本ですが、初期の発生したばかり・柔らかい状態であれば水槽内の生き物が食べてくれることもあります。
アオミドロを食べてくれる生き物と一例として、
- ヤマトヌマエビ
- ミナミヌマエビ
- サイアミーズ・フライングフォックス
- ブラック・モーリー
などがいます。
またタニシもアオミドロを直接は食べませんが、アオミドロの発生原因になる水中の養分や植物プランクトンを食べてくれる点では間接的にアオミドロの抑制に役立ちます。ただし成長したアオミドロは固くなってヤマトヌマエビなどでも食べるのは困難なので、その場合は薬品を使ったり手で取り除くしかなさそうです。

薬品はそれなりに熟練した人じゃないと扱うのは難しそうです。初心者の方や自身のない人は次の2つ『水草を入れる』『手で取り除く』の方が手軽にできますね。

アオミドロは水中の養分をもとに成長します。逆に養分が少ないとアオミドロは成長しづらくなります。その点で水草は種類にもよりますが『水中の養分を吸収する』というメリットがあるので、水草を入れることもアオミドロの抑制には効果的です。
基本的にほとんどの水草は養分を吸収する効果は大なり小なりありますが、特にホテイアオイやアマゾンフロッグピットなどの『浮き草』の類は水中の養分をよく吸収してくれます。

これを言うと元も子もないかもしれませんが、アオミドロは地道に手で取り除くのがある意味一番確実です。アオミドロなどの藻を取り除く薬品もありますがメダカなどのへの生体のリスクがありますし、一時的に別の水槽に移すとしても別の水槽を準備するなどで意外と手間がかかります。
いかに日々水槽を観察して、早い段階でアオミドロを取り除くことができるかがポイントになります。

手間がかかりそうに思えますが、ピンセットなどを水中に入れればアオミドロが絡みつくので早い段階なら簡単にアオミドロを取り除けます。
冬のアオミドロにも注意

アオミドロは夏によく発生しますが、冬でも発生します。画像のように1月で水温が10℃を切るような環境でも意外とアオミドロは見られました。冬はメダカも活動しなくなるとはいえ、水温が10℃くらいになるとある程度動くのでその中でアオミドロがあると夏同様に、メダカがアオミドロに絡まってしまうなどの被害も考えられます。
ただし、冬にアオミドロを取り除こうとすると水を多少なりともかき回すときに本来寒さで動かないメダカを無理に動かすことになりメダカの負担になります。よほどアオミドロがたくさん発生している状況でなければ冬のアオミドロはそこまで気にしなくても良いかもしれません。
アオミドロは早めに取り除こう
- 水槽内(特に屋外)で見られる細かい毛のような藻は『アオミドロ』という名前
- アオミドロの発生原因は大きく『直射日光が当たりすぎ』『富栄養化』の2つ
- アオミドロが増えると水槽内が観察しづらくなる
- アオミドロにメダカなどの生き物が絡まることもある
- アオミドロ対策としては『日陰を作る』『ヤマトヌマエビなどのアオミドロを食べる生き物の導入』『水草を入れる』『手で取り除く』が有効
ほんの少しあるだけならこれといった被害はないアオミドロですが、増えすぎればメダカが絡まってしまうなどの被害もあります。また被害を抜きにしても、水槽の景観が乱れるという点で見た目重視の方に関してもアオミドロはあまり良いものではないかもしれません。
アオミドロ対策としては手で取り除いたり、ヤマトヌマエビに食べてもらったり、薬品を入れたりなどいろいろありますが、いずれにしても『早め』の対処が重要です。
日々の水槽の観察を怠らず、アオミドロを見かけたら早めに対処しましょう。
メダカ用品のお買い物をおトクに!
 涼しげメダカノート
涼しげメダカノート